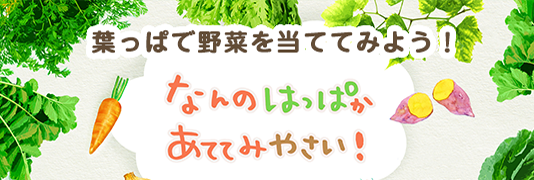松原市で代々続く農家を継承し、大阪メロンと難波葱の栽培に注力する森川ファームの森川さん。空間デザイナーとしての経歴を活かし、可能性いっぱいの農業を楽しみながら農業の未来図を設計しています。その農家ストーリーを伺いました。
◇Profile
森川ファーム園主・森川義之さん

大阪府松原市で1688年から代々続く農家、「森川ファーム」の園主、森川義之さん。デザイン設計の仕事から専業農家に転身し、新しい農家のスタイルを築きたいという思いで、さまざまなことに挑戦中。
公式HP:https://www.morikawa-farm.com/
公式SNS:https://www.instagram.com/morikawa.farm/
■12代目が紡ぐ農家の未来|設計士から専業農家への転身

松原市の幹線道路から少し入ったところに広がる森川ファームの農地には、収穫を終えたメロンのハウスが並び、青々とした葱の畝が続きます。ここでこだわりの大阪メロンと難波葱を栽培しているのは、代々続く農家を継承して12代目の園主となった森川義之さんです。
繁忙期は農業を手伝いながら、建物や空間デザインなどを手がける設計事務所の代表として精力的に仕事をしていた森川さん。仕事と兼業して好きな農業に取り組む父の姿を見ていて、いつかは継ぐつもりだったと話します。「父は好きなことをやればいいと言ってくれていましたが、9年前に亡くなった時、仕事をやめて農業をする時が来た!と思いましたね」と振り返ります。
■農への第一歩|無農薬・有機栽培へのこだわり

代々継承してきた農地があり、人件費削減のために導入していた農機具も揃っているという環境で、「ものを作ることが好きでとことん突き詰めるタイプ」という森川さんは、設計事務所を整理して専業農家になる決断をしました。
「米作りの手伝いをしてきたとはいえ、本格的な農業は無知な状態で一からのスタートでした」。そんな森川さんが、まず手がけたのは季節ごとに栽培する少量多品目栽培の野菜。作るものに対してこだわりたいという思いから無農薬、有機栽培をめざして、人に聞いたり本を読んだりしながら知識を深めて改良した結果、納品先の飲食店から高評価をもらえるようになりました。
■至高の一果を求めて|一樹一果の大阪メロンへの挑戦

成果を感じた森川さんが、農業のさらなる展開を求めて始めたのが、元々やってみたいと考えていたメロン栽培への挑戦です。近くには教えてもらう人がいないメロン栽培への挑戦は、全国の農家とSNSで繋がって親身になってくれる人との出会いもあり、2022年にスタート。ここでも、設計事務所時代の信条、「やるからにはとことんやる!」を実行した森川さんは、卸していた野菜はすべてストップした上でメロンに集中しました。
森川さんが取り組んでいるのは、「一樹一果」の栽培方法。「おいしいものを作ることにこだわって、食べた人に感動してもらいたい」という根底にある思いを実現するために選択した方法です。
■情熱が実を結ぶ|失敗を乗り越え、広がる可能性

「メロン栽培は温度やタイミングが重要で、朝から晩までつきっきりで1日15回もハウスに足を運んで見守っていました」。その甲斐あって、1回目の収穫は大成功!教えてくれた人も絶賛するほどの出来でした。
翌年は雨が多くて実割れが起こったり、甘さが乗る最後の1週間に気温の上下があって納得のいくものが少ししか採れなかったり、順風満帆なことばかりではないことも。

そんな中でも、大阪メロンを応援してくれる企業とのコラボが実現。今年も6月ごろから、桜珈琲で大阪メロンを使ったメニューが登場予定で、他にも加工商品の開発など、ブランド確立に向けて歩みを進めています。
■受け継がれる味|祖父から繋ぐ難波葱の伝統

森川さんがもう一つ、力を入れて栽培しているのが伝統野菜「難波葱」。日本の葱の原種と言われ、衝撃を受けるくらいの甘みに加え、やわらかくて口に残らないのが特徴です。「祖父が難波葱を作っていて、小さい頃は収穫した葱から出るぬめりで遊んだ記憶があるんですよ」という思い出のある作物です。
畑では、あえてそのままにしている草と一緒に青々とした難波葱が元気よく育っています。11月下旬から3月上旬まで栽培・収穫し、大阪府下の大手スーパーでも取り扱われています。森川さんは、「全国ねぎサミット」にも参加して難波葱の魅力を全国に発信するとともに、「JA大阪中河内難波葱部会」の一員として、なにわの伝統野菜である大阪産の難波葱の伝統をつないでいます。
全国ネギサミットの情報はこちらから:https://www.city.mito.lg.jp/page/69512.html
■デザインと農業の交差点|創造性が育む感動体験

「全く畑違いとは思いません」と、前職の設計事務所での仕事から専業農家へと転身した森川さんは言います。ゼロから空間をデザインする仕事もおいしいものを作る農業も、こだわりを持って取り組むことで相手に感動を届けることができます。
また、人とのつながりが重要なところも共通点。技術の習得や販路の交渉などでは、職人さんや取引先とのやりとりと同じように、人を大事にする姿勢が物事をスムーズに進めます。お客様に喜んでもらうという目的は同じで、住みやすい空間、おいしい作物を作るために工夫するという、どちらもクリエイティブな仕事です。
■次世代へ種を蒔く|感動を育てる農業の可能性

「メロンは息子が好きな食べ物ということもあるんですよ」。独自性のあるものづくりをして、農業の魅力を伝えること。そこには、「息子に農業を引き継いでもらうには」というもうひとつの視点もあります。
一方、桜珈琲では社員教育のために生産者として話をする機会を持ったり、保育園給食に使う米や野菜の出荷を通じて食育に関わったり、森川さんが農業への理解を推進するための活動は多岐にわたります。
「森川ファームで、作って加工するところまで一連の農業の流れを体験できるような場を用意して、食べるものに対する価値観を共有したい」と今後の展望を語る森川さん。「利益よりもお客様を笑顔にして感動してもらえること」を第一義にするからこそ、どの仕事も楽しんでこられたということがよく伝わります。息子さんが大阪メロンをさらに発展させる未来が見えてくるようです。
また、若い世代の農業者が中心となり、経営や技術の解決方法を検討する「大阪府4Hクラブ」にも参加し、将来の日本の農業を支えるためのプロジェクト活動のほか、消費者や他クラブとの交流、地域のボランティア活動にも貢献しています。
■Message|農業という生きる力

農業はした分だけ自分に返ってくる仕事です。楽しみながら、突き詰めてやって欲しいと思います。朝から晩まで時間をフルに使う仕事ですが、自分自身でマネージメントすれば充実した時間を過ごせます。自分で作って売るところまで、ものすごく可能性があってワクワクしながら取り組める仕事です。農業は生きる力。食べないと生きていけない。シンプルだけど重要でクリエイティブなこの仕事にぜひ携わってみてください。

 本サイトについて
本サイトについて