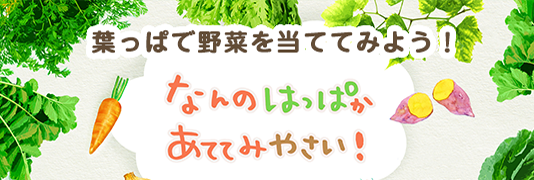和泉市でミニトマト専業農家として、栽培と観光農園を運営するキノシタファーム。営業職として得た経験のすべてを農業に反映させた、その農業スタイルとは?親の農業を継承せず、自分のスタイルを見いだして前進を続ける代表の木下さんにお話を聞きました。
◇Profile
キノシタファーム代表・木下健司さん

大阪府和泉市・岸和田市でこだわりのミニトマトを栽培する「キノシタファーム」代表の木下健司さん。農家に生まれ大学卒業後に商社、食肉卸、製紙メーカーに勤めた後、就農。多様な営業職で得た経験を活かして、幅広い視点で農業を展開中。
公式HP:https://kinoshitafarm.com/
公式ECサイト:https://amamade.thebase.in/
戦略性の高さを「大阪 ミニトマト」で検索して体感してみてください!
■農業したいと言った瞬間、始められる環境がある!

170号線沿いの道の駅いずみ山愛の里の駐車場から見えるハウスが「キノシタファーム」。大阪府下の農産物直売所や百貨店、スーパー、ネット通販などで販売され、料理人にもファンが多いミニトマト「アマメイド」を栽培し、3月~7月のシーズンにはミニトマト狩りも行っている農園です。
園主は農家の長男として育ち、営業職としてバリバリ仕事をしていた木下さん。「30歳の節目を目前にして、農業をやってみるのもいいかなと」。軽く考え始めていた木下さんの背中を押したのが、「農業したいと言った瞬間、始められる環境があるってめっちゃええやん!」という先輩の言葉でした。
■トマト嫌いが驚いた美味しいミニトマトを作る!

新規就農でもなく、親の農業をそのまま代替わりするのでもなく、その中間で自分なりの農業を追求するという就農スタイルを選んでスタートしたのが29歳の時。「同じことをしたらケンカすると思って(笑)」と、小松菜や水菜を栽培していた父から得た知識や人脈の恩恵に感謝しつつも直接引き継ぐことはせず、土地は借りて栽培する品目も経営も別にしました。
「あの日、雨が降ってなかったら」と振り返る29歳の11月、農作業が休みだった木下さんは大阪府の経営講座でミニトマトのバッグ栽培に出会います。「実は、トマトは嫌いだったんですが、初めて美味しいと思うトマトに出会ったんです」。この感動からビジネスの可能性を見いだし、川合肥料で半年間の研修を受け、本格的にミニトマト栽培をスタートしました。
■ミニトマトの可能性を確信してバッグ栽培を導入

ミニトマトへの確信が芽生えたのは、研修時代に参加したあるイベントがきっかけでした。「正直、トマトなんてそんなに売れないだろうと思っていたら、1カップ100円のミニトマトがむちゃくちゃ売れたんです。子どもたちが『美味しい!』と言って何度もお代わりしてくれて」。
「餅は餅屋という考えで、肥料会社が作った土を使ったバッグ栽培なら、良いものができるだろうと思いました」と話す木下さん。バッグ栽培は栽培環境を清潔に保てる利点もあり、この時点で既に、バッグ栽培によるミニトマト狩りの観光農園を展開するという構想を描いていました。地域で初のトマト専業農家として、地元のJAいずみのとも協力しながら、地域活性化の推進にも積極的に取り組んでいます。

数字の目標を立て、それを達成するための方法を考え、課題があれば迅速に対応していく。商社、卸売、メーカーという異なる業界で培った営業経験を農場経営に活かし、親世代の農業とは異なる視点から収益性向上を追求しています。
コロナ禍の初期には、素早くネット販売を立ち上げました。初年度こそ爆発的に売上が伸びたものの、3年後には売上が激減しました。当初は、動き出しの早い企業が少なく、いわばブルーオーシャンの状態でしたが、コロナ禍の長期化により多くの農家や事業者がECに参入。オンライン販売市場が急激に飽和し、競争が激化したことが要因でした。
しかし木下さんにとっては、こうした局面も想定内のこと。現在は、年間収穫量を30トンから40トンに引き上げることを目標に掲げており、その実現に向けて施設の拡張や気候変動への対応といった新たな課題に日々挑戦しています。
■ブランド名「アマメイド」に込めた思い

ブランド名の「アマメイド」は、「人と魚の間のマーメイドのように、酸味と甘みを併せ持つ」「甘い(アマ)を作る(メイド)」という2つの意味を込めて名付けられました。あえて高付加価値路線ではなく、糖度8度を基準として、裾野を広げ、安定的に売れるラインを目指したミニトマトづくりを心がけています。JAいずみのと協力し、発芽率の向上にも成功。安定して美味しいミニトマトを届けるための取り組みを続けています。

また、ロゴやイラストのデザインには惜しみなく費用をかけ、トマトを入れる袋にもこだわりが。地元の顔が見える範囲で販売するものには木下さん自身の写真入りを使い、全国発送向けには写真なしと使い分けています。こうした細かな工夫からも、ブランドに対する強い思いが伝わってきます。
「よく売れるようになれば、売るための労力が不要になります。その時間を栽培に集中することで、さらに美味しいミニトマトを届けられる。するとまた買ってもらえるという、良い循環が生まれるんです」。農家の使命は、美味しいものを作ること――ここが絶対にぶれてはいけないポイントだと、木下さんは教えてくれました。
■「一人では広げきれない」だから、共に育て、共に売る

現在、キノシタファームは社員2名とパート10名の体制で運営しています。スタッフの雇用にはJAの無料職業紹介制度を活用し、繁忙期にはスポット雇用も積極的に取り入れています。また、社内ではスタッフから提案された効率化アイデアを積極的に採用することで、経営への参加意識の向上にもつなげています。
「ミニトマト狩り 大阪」と検索すると、表示されるのはキノシタファームだけ。この強みを守りつつ、さらに事業を拡大していくためには、事業を継承できるスタッフの育成が不可欠です。
「全部を一人でやるのはキャパオーバー」と語る木下さん。現在は、独立を目指す社員に対して、栽培技術や運営ノウハウの継承を行いながら、販路やブランドの共有など、共に育て、共に広げる仕組みづくりを進めています。
■次世代に農業の魅力を伝えて未来を託す使命を担う

「観光農園を事業の柱としてもっと底上げしていきたい」と、今後のビジョンを語る木下さん。道の駅にキッチンカーを呼んだり、みかんやいちご農家とコラボレーションしたりと、地域ぐるみの観光農業による地域活性化も構想しています。これまで大阪府農協青壮年組織協議会の委員長や4Hクラブの会長を積極的に務め、リーダーシップを発揮してきた木下さんならではの発想に期待が高まります。
「話すことは苦にならないので」と営業職時代のスキルを活かし、自身の経験をもとにしたセミナーなどで農場経営のノウハウを惜しみなく伝える木下さん。これまで取材してきた農家さんが、キノシタファームをよく話題に挙げる理由も納得です。
経営を安定させて自身の負担を軽減し、次世代のスタッフに農業の魅力を伝え、未来を託していくことも重要な使命の一つ。「ヘッドホンで小説を聞きながらやれば、撤去作業だって楽しめますよ」と笑顔で話す木下さんの探求心と向上心は尽きることがありません。「思いつきで始めた」という農業ですが、その可能性をさらに広げ、私たちに明るい未来を見せてくれるに違いありません。

 本サイトについて
本サイトについて